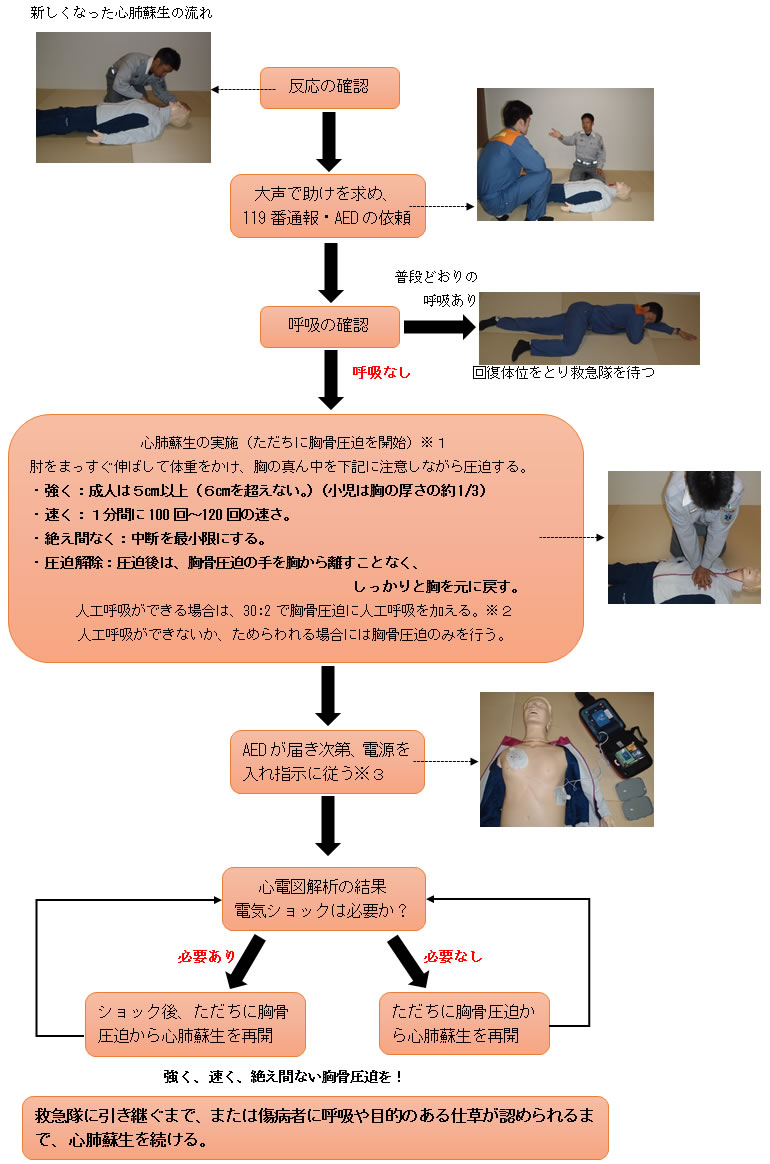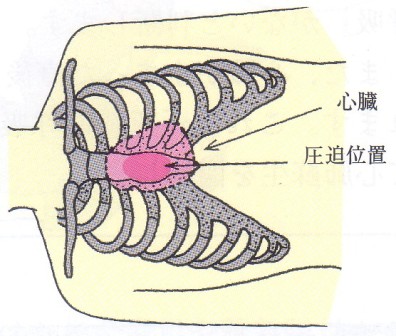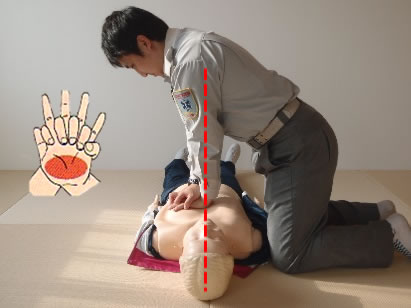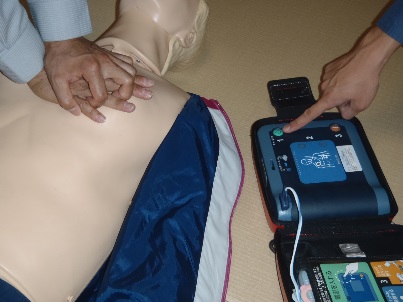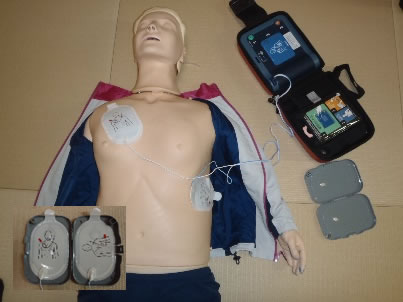JRCガイドライン2015
JRC(日本版)ガイドライン2015の公表を受け、北はりま消防本部では、新しいガイドラインに基づく応急手当の講習を開始しました。
新しくなった心肺蘇生法の流れ(クリックすると拡大します!)
1胸骨圧迫(写真をクリックすると拡大します!)
2人工呼吸(写真をクリックすると拡大します!)
 |
1.気道確保 頭側の手のひらを傷病者の額に当て頭を後ろに反らせます。 足側の手の人差し指と中指の2本で、傷病者のあご先を上方に持ち上げます。 |
 |
2.人工呼吸 気道確保の状態のまま、額に当てた手のひらの親指と人差し指で、傷病者の鼻をつまみます。 次に、傷病者の口を覆うように自分(救助者)の口を被せ、傷病者の胸が軽く上がる程度、息を1秒掛けて吹き込みます。 この動作を2回繰り返します。 |
3AED使用方法(写真をクリックすると拡大します!)
ガイドライン2015に準拠した心肺蘇生法
|
年齢区分 (目安の年齢) |
成 人 (15歳以上) |
小 児 (1歳から15歳まで) |
乳 児 (1歳未満) |
|
|
通 報 |
反応がないと判断した場合、または反応があるかどうかに迷った場合には、直ちに大声で助けを求め、119番通報とAEDの手配をする。 |
|||
|
心停止の判断 |
普段どおりの呼吸が見られない場合、または心停止の判断に迷った場合。 |
|||
|
胸骨圧迫 |
位 置 |
胸骨の下半分(目安として胸の真ん中) |
||
|
方 法 |
両手 |
両手、または片手 |
指2本 |
|
|
深 さ |
5㎝以上(ただし6㎝を超えない。) |
胸の厚さの約3分の1 |
||
|
速 さ |
毎分100~120回 |
|||
|
人工呼吸 |
約1秒かけて、「胸の上がりが見える程度」の量を送気(2回) |
|||
|
胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ |
1人法、2人法とも 30:2 |
1人法 30:2 2人法 15:2 |
||
|
AEDパッド |
成人用パッド |
就 学 児:成人用パッド 未就学児:小児用パッド もしくは小児モード ※小児用パッドがない場合 成人用パッドの代用可能 |
小児用パッド もしくは小児モード ※小児用パッドがない場合 成人用パッドの代用可能 |
|
応急手当の方法は、さまざまな研究や検証を重ね、原則5年毎に、より良い方法へ改正されています。新しい応急手当の方法は、それまでの方法を否定するものではありません。
大切なことは、目の前に倒れている人を救うために「自分ができることを行う」ことです。
緊急の事態に遭遇したときに適切な応急手当てができるように、日頃から応急手当を学び、身につけておきましょう。